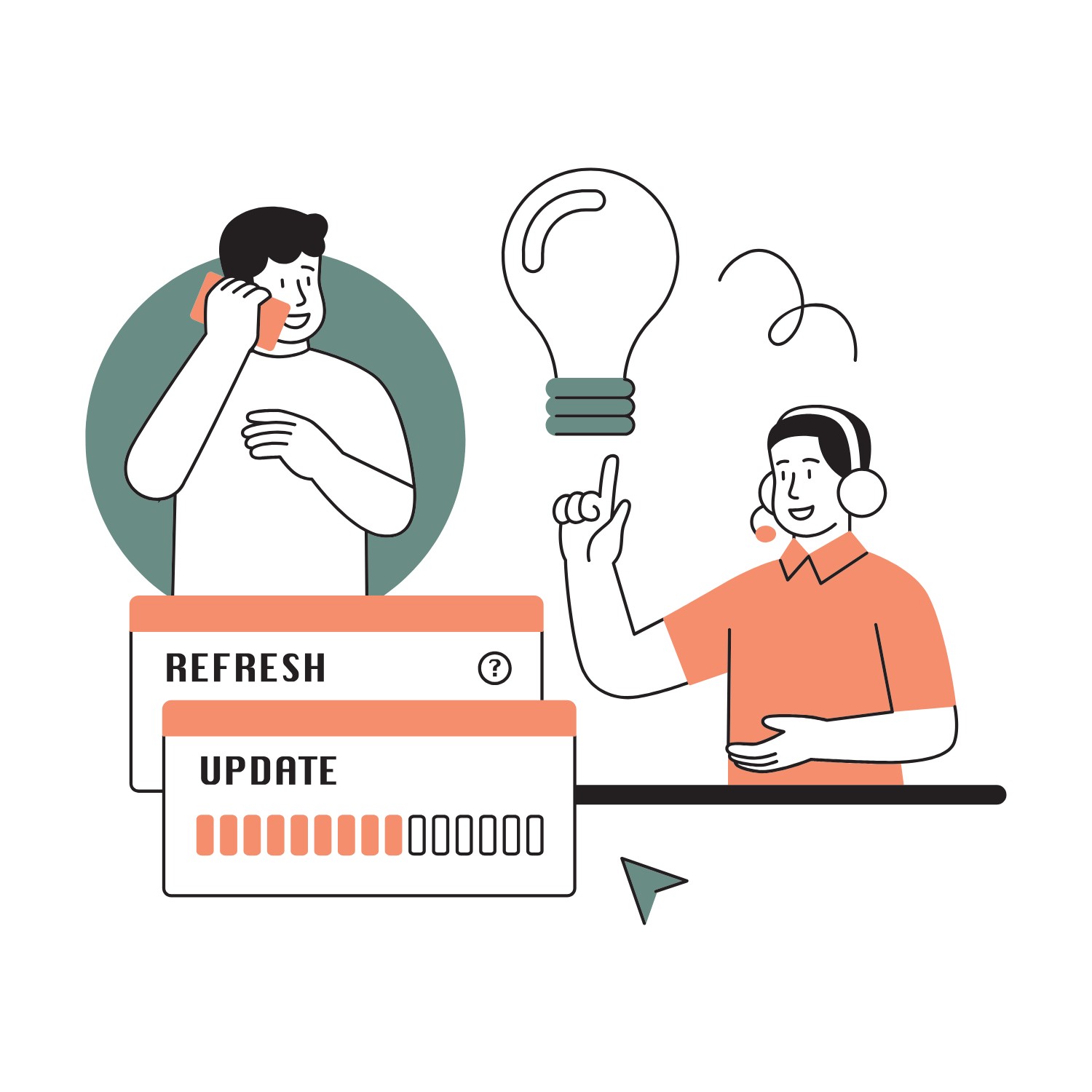“なんとなく良さそう”では売れない|越境ECで必要な「買う理由」のつくり方 -和食器ブランドがフランス市場で支持された理由-
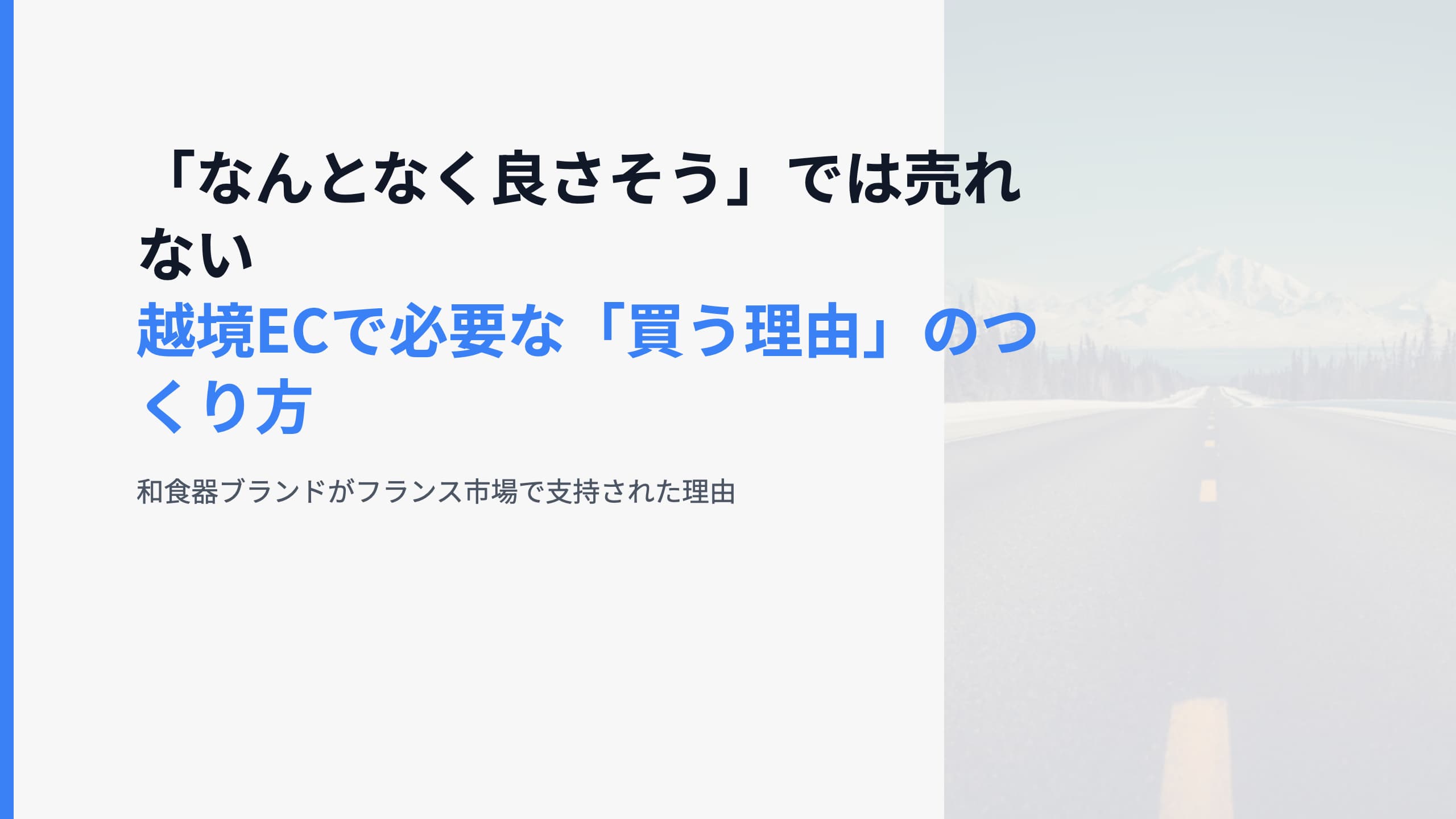
「海外でも人気だから売れるはず」
「広告をかければ広がるだろう」
越境ECでそんな期待を持って始めたものの、思ったように売れなかったという声をよく聞きます。
その多くに共通するのが、“なぜ買うのか?”というコンセプトが言語化されていないことです。
本記事では、日本の和食器ブランドがフランス市場で成功した事例をもとに、海外の顧客に伝わる「売れるコンセプト」の設計法を解説します。
「売れるコンセプト」は、顧客の“願望”と言葉でつながっている
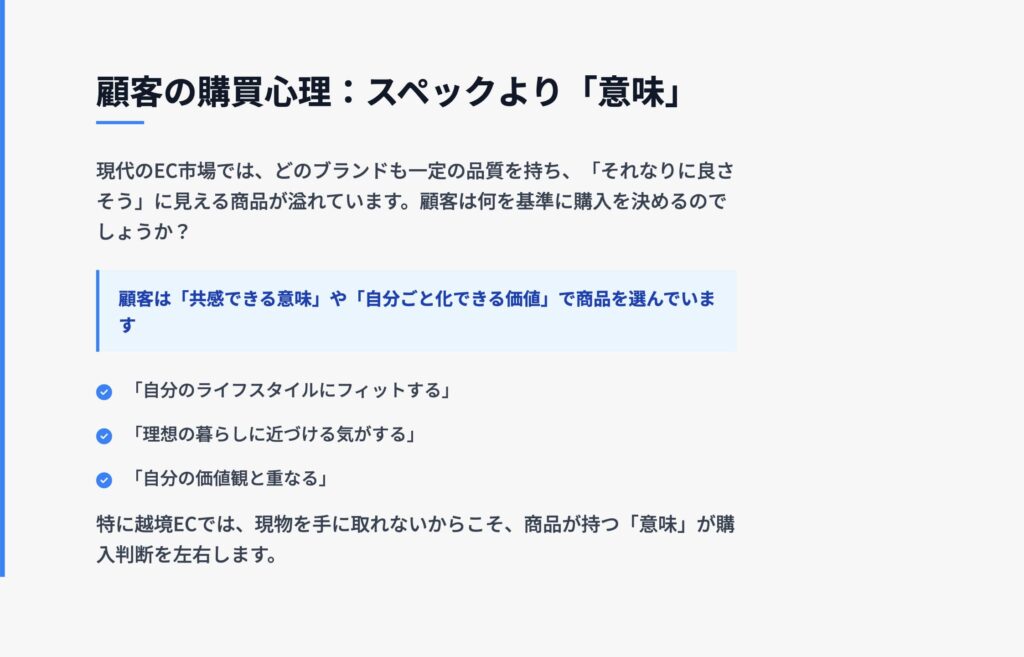
スペックではなく、「意味」で選ばれる時代
現代のEC市場では、どのブランドも一定の品質を持ち、“それなりに良さそう”に見える商品が溢れています。特に越境ECにおいては、現物を手に取ることができないため、なおさらスペックや写真だけで差別化するのが難しくなっています。
このような環境の中で顧客が最終的に何を基準に購入を決めているかというと、それは「共感できる意味」や「自分ごと化できる価値」です。
「なぜこの商品を選ぶのか?」という問いに対して、
- 自分のライフスタイルにフィットする
- 理想の暮らしに近づける気がする
- 自分の価値観と重なる
といった感情レベルの納得が得られることが、今の消費行動における重要な判断軸になっています。
つまり、選ばれるブランドとは、商品そのものではなく「その商品が持つ意味」を伝えられるブランドなのです。
必要なのは「意味づけの言語化」
では、その“意味”をどうやって伝えるのか。ここで鍵になるのが、「意味づけの言語化」です。
単なる商品説明ではなく、以下のような要素をつなぎあわせて言葉に落とし込むことが求められます。
- 商品の強み(素材・技術・デザイン)
- 顧客の願望(こうなりたい、こうありたいという気持ち)
- 使用シーン(その商品が日常の中でどう機能するか)
この3つが重なったときに、ようやく「これはあなたのための商品です」と伝わるストーリーが生まれます。
たとえば、ただ「手作りの和食器」と伝えるのではなく、
「週末の朝食を、ちょっと丁寧にしたい人へ。手仕事のぬくもりが、暮らしのリズムを整えてくれる。」
といった言葉に変換することで、「自分のことだ」と感じてもらえる接点が生まれます。
顧客にとっての“買う理由”とは、スペックではなく意味の設計。
そのためには、まず自社の商品に込めた価値を、お客様の言葉に翻訳するプロセスが必要なのです。
事例|和食器ブランドがパリで受け入れられた理由
「日本の職人技」を伝えても売れなかった
ある日本の和食器ブランドは、越境ECを活用してフランス市場、とくにパリを中心に販路拡大を試みていました。ブランドが最初に打ち出したコンセプトは
「日本の伝統技術が光る、手作業による高品質な器」
いわば“日本の誇り”をストレートに伝えるものでした。
確かにこのメッセージは一定の反応を呼び、パリの雑貨バイヤーや和食好きの一部層には「面白い」「美しい」と認知されました。
しかし、肝心の売上にはなかなかつながらなかったのです。
ページの閲覧数はある、SNSでも紹介される。それでも“買う人”は限られていました。
転機は「ライフスタイル提案」へのシフト
そこでブランド側は、現地の購入者・非購入者にインタビューを実施。
その中で浮かび上がったのが、パリの顧客が持っていた“暮らしに対する憧れ”や“商品への期待値”のズレでした。
とくに印象的だったのは、以下のような声です:
- 「毎日を丁寧に暮らしたい。そんな時間を演出してくれる食器が欲しい」
- 「器は自己表現の一部。洋服のように“自分らしさ”を表したい」
- 「贈り物を選ぶとき、その背景にストーリーがあると嬉しい」
つまり、彼らが求めていたのは「技術の高さ」ではなく、器を通じて得られる体験や感情の価値でした。
これを受けてブランドはメッセージを再設計。
「伝統と技術」ではなく、「あなたのライフスタイルを彩るパートナー」として和食器を再定義し、暮らしのシーンやギフト用途を軸にコンテンツを展開しました。
結果的に、“共感できるコンセプト”が伝わるようになり、売上もフォロワー数も着実に伸びていったのです。
「買う理由」をコンセプトに落とし込む
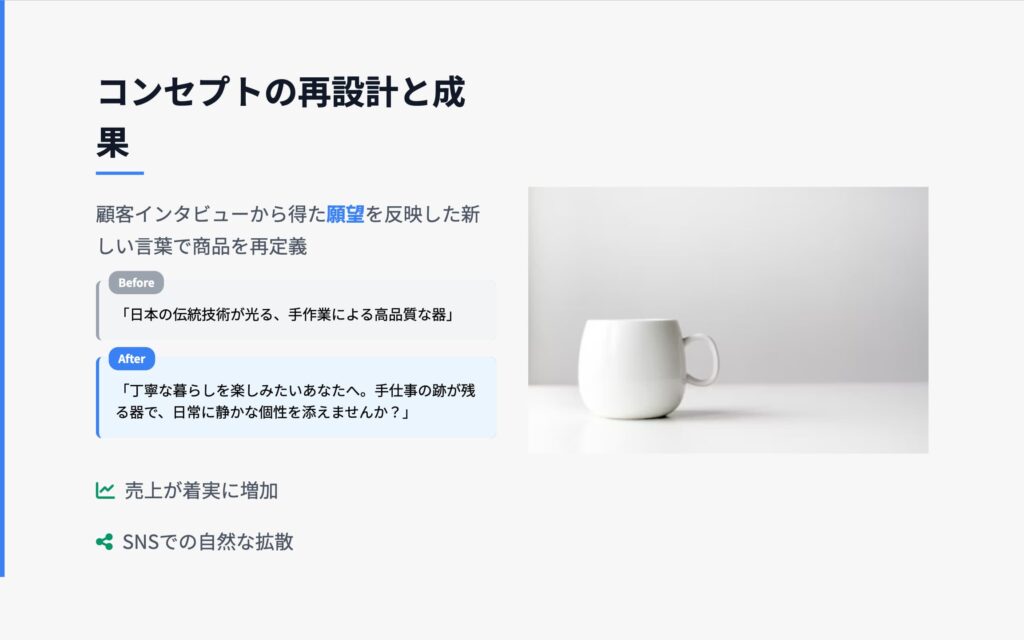
新たなコンセプトの言語化例
パリの顧客インタビューを通じて、「丁寧な暮らしをしたい」「器を通じて自分を表現したい」という“願望”が見えてきたことで、ブランドは商品の立ち位置を根本から見直しました。
単なる「日本製の美しい器」ではなく、次のような言葉で再定義したのです。
「丁寧な暮らしを楽しみたいあなたへ。手仕事の跡が残る器で、日常に静かな個性を添えませんか?」
この一文には、以下の3要素が含まれています。
- 顧客の願望:日常を美しく整えたい、自分らしく過ごしたい
- 商品の特徴:手作業ゆえに一つひとつ表情が異なる器
- 使用シーン:日常の食卓、週末の朝食、友人との時間など
これにより、顧客は「これは私の暮らしに合うかも」と自分ごととして想像できるようになりました。
コンセプトは「翻訳作業」でもある
売れるコンセプトとは、商品の魅力そのものではなく、それが誰に・どんな状況で・なぜ必要とされるのかを、ターゲットの言葉で伝えるものです。
職人の視点からすれば「釉薬の発色」「高台の仕上げ」などが魅力でも、それが直接購入理由にはなりません。
顧客の中にある“言語化されていない気持ち”をくみ取り、
それに商品がどう応えるのかを共通の言語にして橋渡しすること。
それが、越境ECにおける「買う理由のデザイン」なのです。
伝える方法|ガイドコンテンツで「意味」を体感させる
ビジュアル × 言葉で“らしさ”を伝える工夫
いくら良いコンセプトを設計しても、それが顧客に届かなければ意味がありません。
とくに越境ECでは、「伝える」ではなく「伝わる」状態をつくることが重要です。
そのために効果的なのが、「ガイドコンテンツ」の活用です。
商品そのものを見せるだけでなく、その商品がある暮らしをイメージさせるような見せ方が求められます。
たとえば、和食器ブランドが実践した工夫
- 「週末の朝」や「友人とのディナー」など、使用シーン別のコーディネート提案
→ 商品単体ではなく、「空間の一部」として登場することで、暮らしの一部として想像しやすくなる。 - 器が届いた日のストーリーを写真と文章で再現
→ 開封から食卓に並べるまでの“体験”をビジュアルで共有。 - 実際の購入者インタビューやSNS投稿の再利用
→ 他人のリアルな使い方や感想は、「自分にも合いそう」と感じさせる最大のヒントになる。 - 贈り物用途の提案:ラッピング例やメッセージカード文例も掲載
→ ストーリー性のあるギフトとしての価値が伝わるよう設計。
商品の魅力ではなく、「暮らしのイメージ」を売る
ガイドコンテンツの目的は、商品の魅力をくどくど説明することではありません。
顧客が商品を見たときに、「これが自分の暮らしにある未来」がイメージできるようにすることです。
つまり、「良さを伝える」のではなく、「使っている自分を想像させる」こと。
これが、“意味が伝わるコンテンツ”の本質です。
結果|価格ではなく“意味”で選ばれるブランドへ
和食器ブランドがコンセプトを再設計し、「意味が伝わる」コンテンツを整えたことで、ブランドには明確な変化が現れました。
「スペック競争」から「共感による指名買い」へ
以前は、競合商品と比較される中で「少し高い」「違いがわかりづらい」といった理由でスルーされることも多く、価格やデザインで選ばれる消耗戦に巻き込まれていました。
しかし、コンセプトと言葉を通じて「これは自分の暮らしに必要なものだ」と顧客自身が感じられるようになった結果、比較対象は“他の商品”ではなく、“その人の理想の生活像”になったのです。
するとどうなるか?
- SNSでの自然なシェアが増える
- 顧客が自発的に「この器があると気持ちが整う」と言語化し始める
- 「高いからやめる」ではなく、「価値があるから買いたい」に変わる
これが、“価格ではなく意味で選ばれるブランド”が持つ強さです。
越境ECにおける本当のブランディングとは?
商品を海外に届けるのは、ただの物流の話です。
でも、「選ばれるブランドになる」には、相手の文化や価値観を理解し、その中で“あなたらしい選択肢”として存在できるかが鍵になります。
フランスの顧客が和食器に見たのは、単なる“日本の技術”ではなく、
「理想のライフスタイルを映し出す小さな道具」としての存在でした。
それを可能にしたのは、意味づけの言語化と、それを体感できるコンテンツ設計です。
まとめ|売れるコンセプトは、言語化と検証の繰り返し

「いい商品を作れば、きっと海外でも売れる」
越境ECを始める多くのブランドが、最初にこの前提を信じます。
しかし実際には、“なぜ自分がこの商品を買うのか”が伝わらなければ、どんなに良い商品でも選ばれません。
顧客が求めているのはスペックや素材ではなく、「その商品を持つことで得られる意味や感情」なのです。
本記事で紹介した和食器ブランドのように、売れるコンセプトを作るには次の3つのステップが必要です:
1、顧客の“願望”を知る
– 購入者・非購入者の声を拾い、「どんな生活を理想としているのか」「なぜ迷ったのか」を理解する。
2、商品の“意味”を言語化する
– スペックではなく、「誰にとって、どんなふうに役立つのか」をお客様の言葉で翻訳する。
3、“伝わる形”でコンテンツに落とし込む
– 写真、ストーリー、使用シーン、インタビューなどを活用し、「これは自分のための商品だ」と感じさせる体験設計を行う。
これらは一度やって終わりではありません。
市場によって、ターゲットによって、「響く言葉」は変わります。
だからこそ、売れるコンセプトは“つくって終わり”ではなく、“育てるもの”なのです。
広告を打つ前に、SNSを伸ばす前に、まず取り組むべきはこの設計。
「なぜあなたの店から買うのか?」
この問いに答えられるブランドだけが、国境を超えて選ばれていくのです。
*こちらの資料は資料ダウンロードからダウンロードできます。